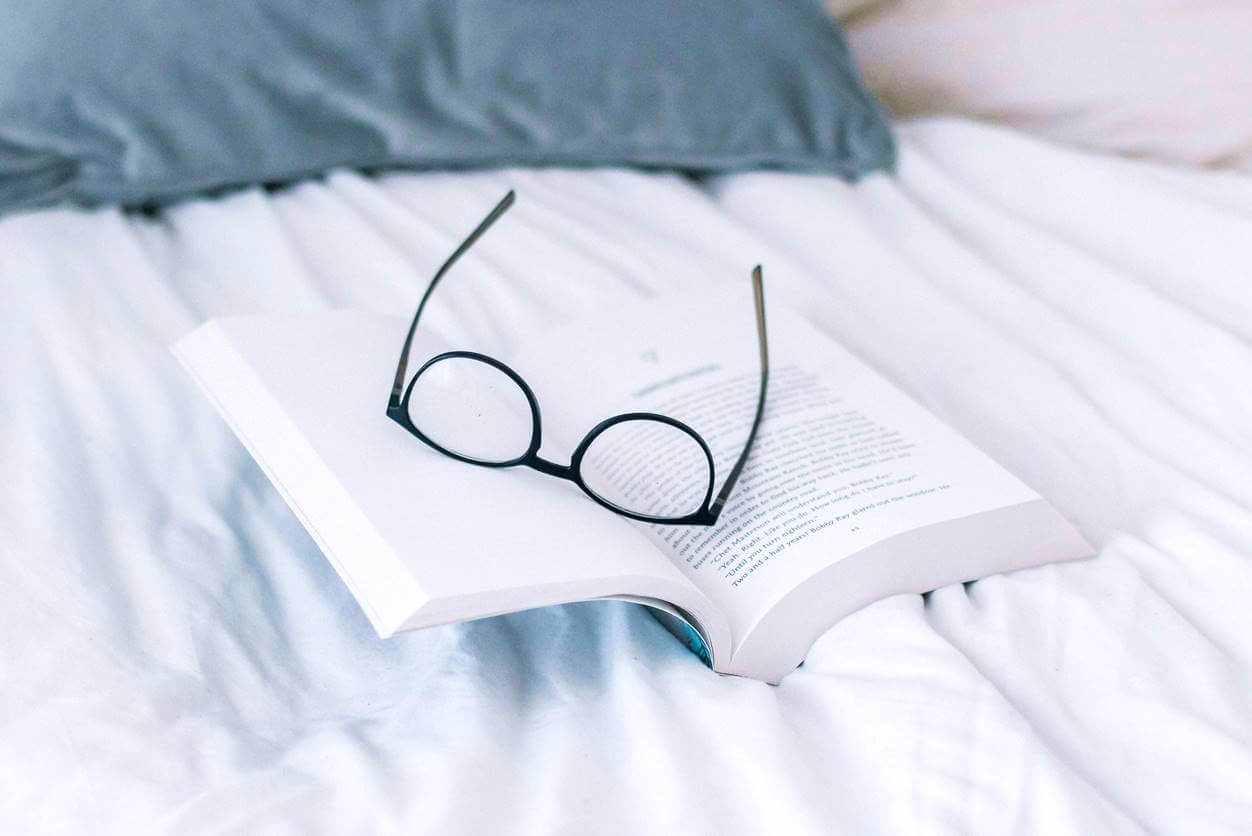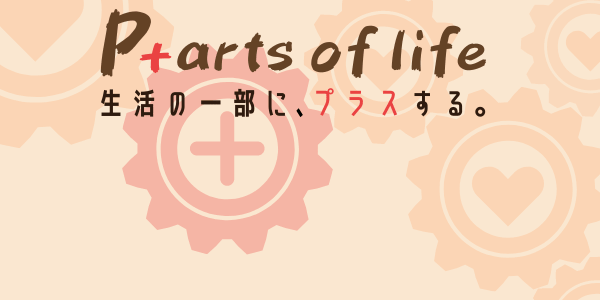※当サイトでは、記事内に広告を含む場合があります。
こんな悩みに答えます。

こんにちは、タストテンです。
うちの猫も、ストレスが溜まると色んな所で爪とぎをします…
賃貸ですと、壁をガリガリしてしまうと敷金などに影響が出てしまいますので、可能な限りやめさせたいですよね。
しかし猫の習性上、爪とぎ自体をやめさせることはできませんので、対策を取る必要があります。

今回は、猫が爪とぎをする理由と、対策方法について解説していきますね
おすすめの爪とぎグッズも併せて紹介しますので、まずはご一読いただけると幸いです。
猫が爪とぎをする理由は5つあります

このような悩みがあると思いますが、猫は様々な理由で爪をといでしまいます。
猫が爪をといでしまう理由については、下記になります。
- 爪を鋭くするため(お手入れ)
- ストレス発散のため
- かまってほしいため
- マーキングをするため
- 背伸びとして(眠気覚まし)
それぞれ解説しますね。
爪を鋭くするため(お手入れ)
猫は、自分の爪を鋭くするために爪とぎをします。
爪を鋭くする行為はお手入れであり、猫の習性なのでやめさせることはできません。
※ただし、普段からこまめに爪を切って整えておくことで、爪をとぐ回数自体は減らせる可能性があります。
ストレス発散のため
猫はストレスが溜まると、ストレスを発散するために爪とぎをする場合があります。
このときの爪のとぎ方は荒く、ストレスを発散している様子がわかりますね。
遊んでくれない、嫌なことがあった場合に荒っぽい爪のとぎ方をするので、ストレスを発散させてあげるようにしましょう。
※猫のストレス解消法については『猫のストレスの解消法5選!ストレスの原因を知って対策しよう』を読んでみてください。
かまってほしいため
猫が遊んでほしいときは、かまってほしい(遊んでほしい)アピールとして爪をとぐ場合があります。
かまってほしそうなときは、無視をせずしっかり遊んであげましょう。
マーキングをするため
爪をといで壁などに目印とニオイをつけることで、マーキングの役割を果たします。
猫は縄張り意識が強いため、マーキングをして縄張りであることをアピールします。
下記のような理由でマーキングを行います。
- 引っ越し
- 家具の配置換え
- 新しい家具の設置
- 家族が増える
- 多頭飼い
- 掃除などでニオイを消してしまう
このように縄張りが変わったり、縄張り争いのためにマーキングをしてしまいます。
背伸びとして(眠気覚まし)
猫は寝起きに眠気を覚ますために体を伸ばしますが、爪で引っ掛けてあくびと一緒に背伸びをし、ついでに爪をとぐことがあります。
これも猫の習性のようなものなので、ポール型の爪とぎで背伸びをしてもらうようしつけるようにしてください。
猫が壁などで爪とぎしないための、おすすめの対策方法4選

猫が壁などで爪とぎしないための、おすすめの対策方法は下記になります。
- 爪とぎのしつけをする
- 爪とぎされる場所を塞ぐ
- 過度のストレスを与えない
- 爪とぎ用のグッズを複数設置する
それぞれ解説しますね。
爪とぎのしつけをする
爪をとぐのは猫の習慣なので、やめさせることはできません。
そのため、『爪とぎをさせる場所』をしつけましょう。
しつける際のポイントは下記になります。
- 爪とぎグッズを、爪をとぐ場所に設置する
- 爪とぎグッズにマタタビを使用する
上記のように、『爪とぎをする場所を、爪とぎグッズに向けさせる』のがポイントです。
猫にとってマタタビは大好きなので、爪をとがせたい場所に使用することでしつけの効果もあります。
※マタタビについて詳しくは、『猫のマタタビの与え方!効果や注意点も徹底解説【与えすぎは危険】』を読んでみてください。
【注意点】しつける際に、大声で叱ったり、叩くのは絶対にダメ
しつけの際の注意点ですが、大声で叱ったり、叩いたりするのは絶対にやめましょう。
猫にとっては、『わけもわからず叩かれた』という感覚なので、ストレスや怯え、嫌われるなど逆効果になります。

絶対に叱ったり叩いたりしてしつけるのはやめましょう
爪とぎされる場所を塞ぐ
爪とぎをされる場所が決まっている場合は、物で塞いでしまうのが効果的です。
- 物を置いて塞いでしまう
- 爪とぎグッズを設置する
- 表面がつるつるしたシートを貼る
上記のように、爪をとがれないように物で塞ぐことで、爪をとぐ場所を制限させることができます。
ただし、この方法ではあくまで『特定の場所で爪とぎをさせないための処置』なので、しつけなどで根本的に対策していきましょう。
過度のストレスを与えない
猫に過度のストレスを与えると、イライラを発散するために爪でガリガリしてしまいます。
猫は環境の変化や接し方、音などの刺激などでストレスを感じるため、不快にさせないように対策していきましょう。
例えば下記のような対策例ですね。
- 寝ているときはそっとしておく
- かまってほしいときはしっかり遊ぶ
- 驚かせるような音を出さない
などなど。
猫のストレスの原因や対策についての詳細は、『猫のストレスの解消法5選!ストレスの原因を知って対策しよう』を読んでみてください。
爪とぎ用のグッズを複数設置する
猫は習性上、爪とぎ自体をやめさせることはできません。
そのため、爪とぎをする場所を爪とぎグッズにさせるのが、いちばん効果的な対策となります。
そこで、僕の猫が気に入っていて、なおかつAmazonでも評価の高い爪とぎグッズを紹介しますね。
猫によって好みの爪とぎグッズがあるため、合う・合わないがありますが、参考になれば幸いです。
【猫用爪とぎおもちゃ】ミュー (mju:) ニャンコロビー ボックス
上面が爪とぎになっていて中に音が鳴るボールが入っているおもちゃです。
手を突っ込んでボールと戯れるのも良し、爪を研ぐのも良し、ボックスの上で寝るのも良しの猫グッズになります。
ただし、本体が軽いので動いてしまうことも。
本体が動いてしまうときは、ボックスの裏側に滑り止めテープなどを貼るのがおすすめです
別バリエーションとして、サークルタイプのものもあります。
おもちゃではありませんが、同社から壁際に置くタイプの爪とぎグッズもあります。
同社から発売されている、猫ベッドにもなる、サークル状の爪とぎグッズもあります。
【ポール型爪とぎ】ポール型つめとぎ(おもちゃつき)
ポール型の爪とぎです。
組み立て式ですが、説明書がいらないレベルで簡単に組み立てることができます。片付けて収納できるのが良いですね。
ポールのてっぺんにおもちゃも付いているので、これで遊べます。
【爪とぎもできる猫用ベッド】猫壱 バリバリベッド
爪とぎ兼ベッドになっています。
この爪とぎベッドはリバーシブルになっていますので、裏返しにして長く使用することができます!
形状が良いのか、うちの猫は気に入って寝床にしています。
価格も安いので、ボロボロになっても気軽に買い換えられるのが良いですね。
【爪とぎもできるキャットタワー】Mwpo キャットタワー
爪とぎもできるキャットタワーです。
遊んだり寝たりでき、ポールの部分で爪をガリガリすることもできます。
室内で高い場所がない場合は、キャットタワーで少しでも高い場所に登らせるようにしましょう。

転倒防止の対策もできるタイプで、Amazonの評判も良いのでおすすめです
【まとめ】猫の爪とぎは習性なので、爪とぎさせる場所を決めてしつけよう

猫の爪とぎは習性なので、爪とぎ自体をやめさせることはできません。
そのため、爪とぎさせる場所を決めてしつけるようにしましょう。
イライラも爪とぎの原因になるため、ストレスの原因も減らしていくようにしてくださいね。
さいごに、爪とぎの対策方法とおすすめの爪とぎグッズを下記にまとめましたので、参考になれば幸いです。
爪とぎの対策方法まとめ
- 爪とぎのしつけをする
→爪とぎさせる場所を決める - 爪とぎされる場所を塞ぐ
→爪とぎをさせたくない場所煮物を置いたりシートを貼り付けたり爪とぎポールを置く - 過度のストレスを与えない
→ストレスの原因を特定してストレスを与えないようにする - 爪とぎ用のグッズを複数設置する
→爪とぎは複数の場所で行うため、たくさん用意したほうがよい
おすすめの爪とぎグッズまとめ
【猫用爪とぎおもちゃ】ミュー (mju:) ニャンコロビー ボックス
別バリエーションとして、サークルタイプのものもあります。
おもちゃではありませんが、同社から壁際に置くタイプの爪とぎグッズもあります。
同社から発売されている、猫ベッドにもなる、サークル状の爪とぎグッズもあります。
【ポール型爪とぎ】ポール型つめとぎ(おもちゃつき)
【爪とぎもできる猫用ベッド】猫壱 バリバリベッド
【爪とぎもできるキャットタワー】Mwpo キャットタワー
🔻おすすめのキャットフードを紹介しています。
🔻Amazonで買って良かったおすすめのキャットフードとおやつを紹介しています。
🔻Amazonで買って良かったおすすめの猫グッズを紹介しています。
🔻無料で3,000円分お試しできる!
あわせて読みたい
[最終更新日]
\ iPhoneを公式ショップで確認 /

[記事を書いた人]タストテン
横浜歴30年以上の横浜大好きブロガー。
ブログ開設1年で年間390万PVを達成。
当ブログ(P+arts:パーツ)では、実体験を基に『暮らしや仕事に役立つライフハックと雑学』を発信しています。
生活の一部として役立てることができれば幸いです。