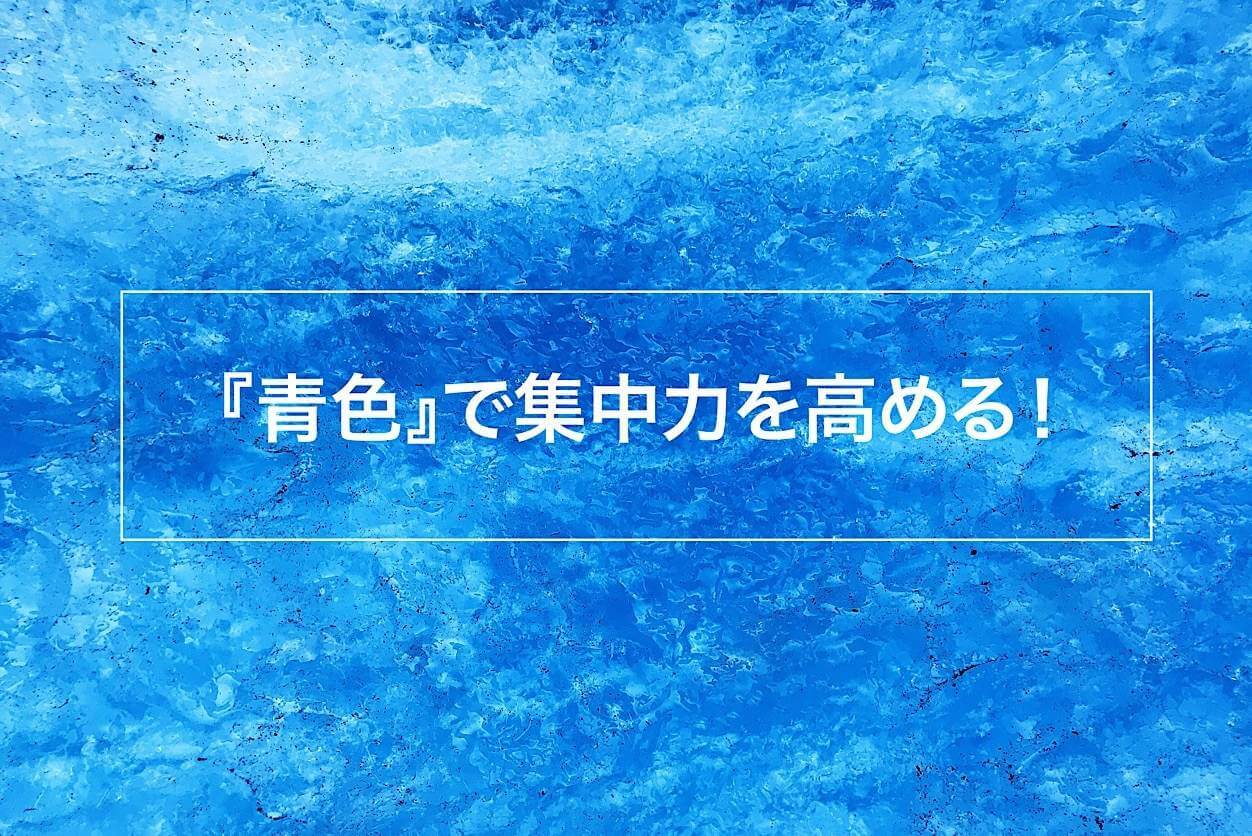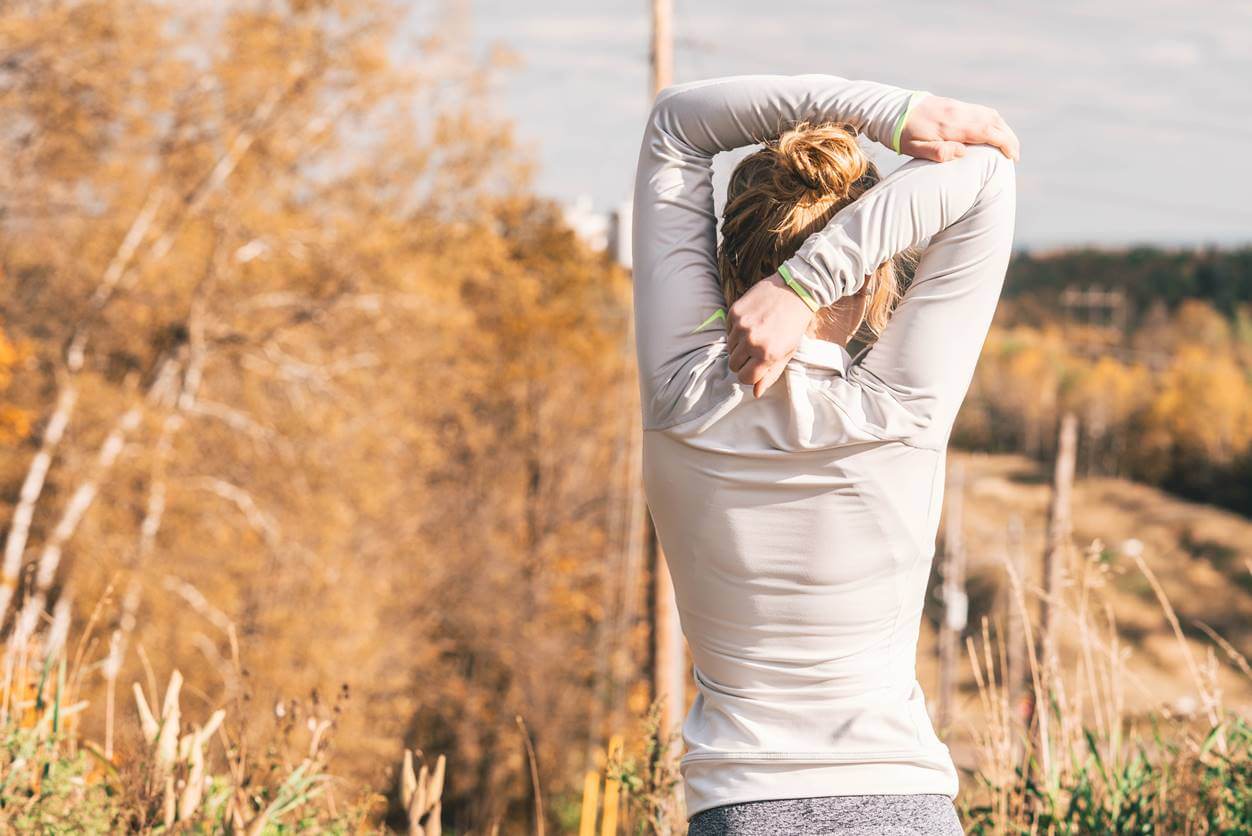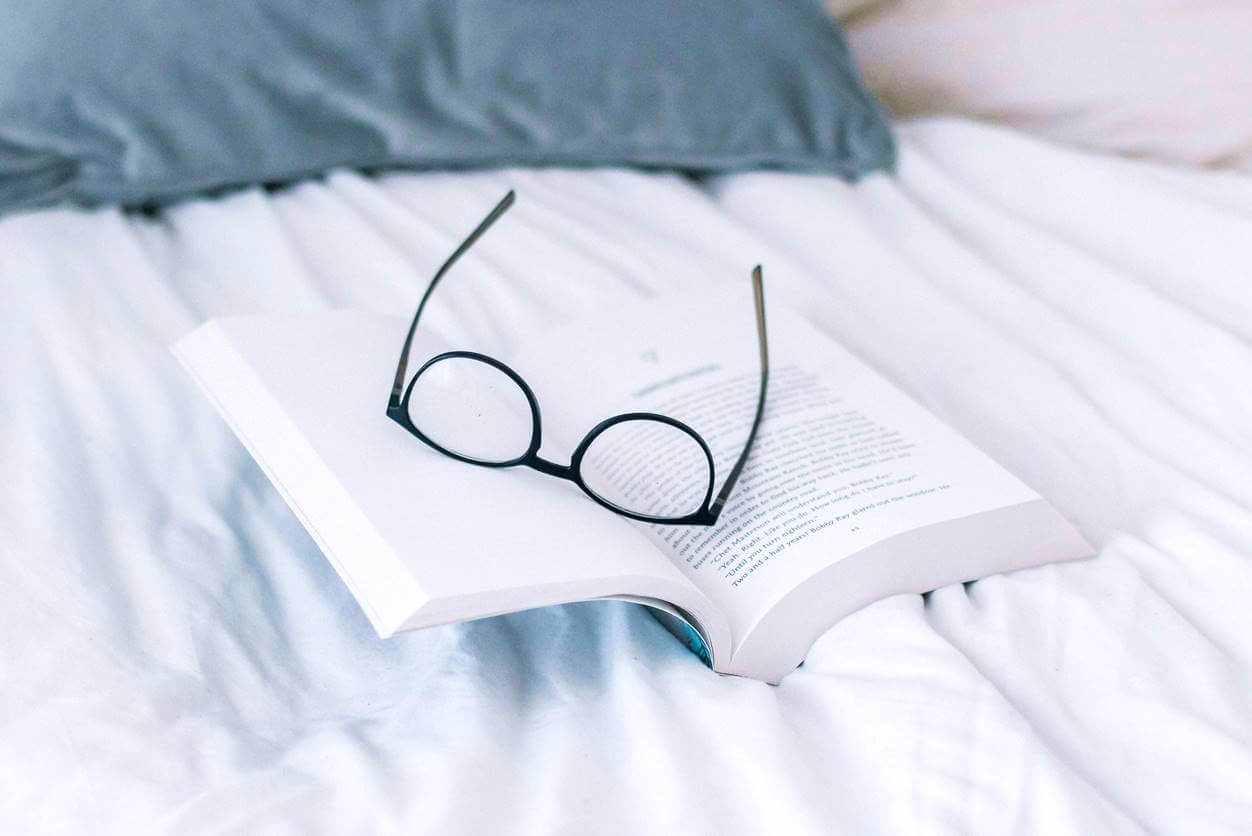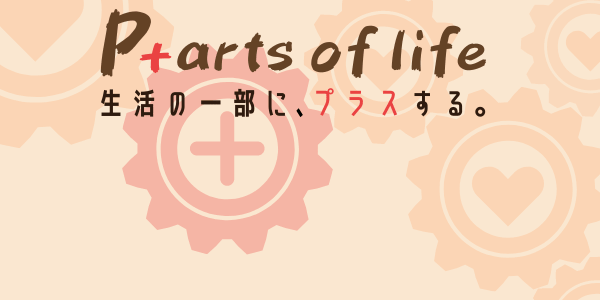※当サイトでは、記事内に広告を含む場合があります。
新年明けましておめでとうございます。
2019年もよろしくお願いします。
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくおねがいします。— タストテン (@tasu_to_ten) 2018年12月31日
こんにちは、タストテンです。
今年の抱負は決まりましたでしょうか?
- 毎年抱負を設定してもほとんど達成できない
- そもそも新年の抱負が思いつかない
そういう人のために、今回は『今年の抱負の決め方』について解説していきます。
新年の抱負は具体的に設定しよう

まずは、抱負の意味について載せておきます。
今年1年の抱負であれば、『今年中に達成したい計画や決意』と置き換えることができます。
ですが、下記のように曖昧な抱負ですとあまり意味をなしません。
- 今年は充実した1年にするぞ!
この場合、『具体的に、何を充実させたいのか』を抱負にする必要があります。
例えばサイクリング好きな人の抱負ですと、
- 今年は1年かけて自転車で日本1周するぞ!
という感じで、具体的に決意をするのであれば、立派な抱負になります。
他にも、
- 今年は朝活でブログを書きたいから2時間の早寝早起きを実践する
- 今年は健康のために毎日1万歩歩く!
などですね。
抱負はあくまで『計画や決意』なので、曖昧な表現ではなく、なるべく具体的に抱くようにしましょう。
新年の抱負を決められないときの4つの考え方

『これだっ!』っていう抱負がなかなか見つからない場合は、以下のことを試してみてください。
- 前年を振り返って、達成できなかったことを抱負にする
- 今やっている趣味や仕事を別の角度から見てみる
- 今年のトレンドを意識して抱負にする
- 身近なものから抱負を決める
ひとつずつ解説します。
前年を振り返って、達成できなかったことを抱負にする
去年の抱負は何でしたか?
去年を振り返ってみて、抱負や目標から、やりたかったことや達成できなかったことを今年の抱負にしてみましょう。
例えば、
- 去年はあまり旅行に行けなかったから、今年は毎月1回は旅行したい
このように、去年できなかっやこと、やりたかっとことを今年の抱負にするのは割と多いですね。
ですが、達成できない抱負を設定して、来年も再来年も同じ抱負にならないようにしましょうね。
今やっている趣味や仕事を別の角度から見てみる
今やっていることについて、別の角度からアプローチをしてみると、抱負が見えてくるかもしれません。
例えば、
- 今までは事務の仕事をやってきたけど、パソコンを使って何かするのが好きだから、今年はプログラミングの勉強をして転職したい
- ゲームが好きだから、YouTuberとして好きなゲームの実況をしながら稼ぎたい
今の状況を別の角度から考えてみると、その人の抱負が見えてくるかもしれません。
今年のトレンドを意識して抱負にする
2019年でいえば、新元号に変わり、増税の可能性があったり、東京オリンピックの前年になります。
このような、トレンドから抱負を考えるのもアリです。
例えば、
- 増税に伴って、税金の仕組みを勉強してお金の負担を少しでも減らしたい
このように、行事ごとや今年流行しそうな出来事をキッカケに何かを始める、計画することはよくありますので、抱負が思い浮かばなければ一考の余地があります。
身近なものから抱負を決める
大きなことをしようと思い、それを抱負にしようとすると、スケールが大きくてイメージがわかないことがあります。
身近なもの、身の回りにあるものから抱負を決めることで、今年の実行したいことを明確にイメージできるようになります。
例えば、
- 仕事で後輩に尊敬されるようになりたいから、ビジネス書籍を毎月5冊読む
- 健康とダイエットのために、1日20分のランニングをする
などですね。
ビジネス書籍を毎月5冊読む、1日20分のランニングという、シンプルでイメージしやすい抱負は実行に移しやすくなります。
新年の抱負はあまり多く設定しても意味がありません
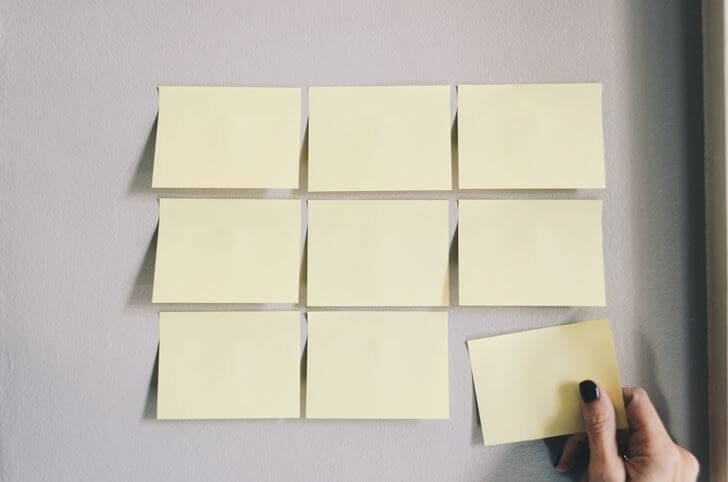
新年の抱負は『数打ちゃ当たる』というものでもないので、あまり多くの抱負を設定しても、実行できなければあまり意味がありません。
日常生活や趣味でひとつ、仕事関係でひとつの計2つぐらいがちょうどいいのかなと感じます。
その辺りは個々の判断になりますが、たくさんの抱負を設定するより数を絞るほうが、ひとつひとつの抱負に向き合いやすくなりますので、実行しやすくなります。
もし去年は抱負を達成できなかったら、今年は抱負の考え方を変えてみると良いかもしれません。
この記事を読んで、少しでも抱負の参考になれば幸いです。
それではまた。
[最終更新日]
\ iPhoneを公式ショップで確認 /

[記事を書いた人]タストテン
横浜歴30年以上の横浜大好きブロガー。
ブログ開設1年で年間390万PVを達成。
当ブログ(P+arts:パーツ)では、実体験を基に『暮らしや仕事に役立つライフハックと雑学』を発信しています。
生活の一部として役立てることができれば幸いです。